会社員として働いていると、「なぜ成果を出しても評価されないのか?」「なぜ成果を出していないのに高給をもらっている人がいるのか?」「このままの事業では会社が衰退してしまう」と疑問に思うことがあると思います。
私自身もこの違和感を強く抱き、組織を変えよう、事業に変化を与えようと行動してきましたが、上手く実行できたことは数少なく、非常に気力も体力も、時間も掛かる作業でした。
そこで気づいたのは、成果や正しさでは覆せない「既得権益構造」が存在するということです。
本記事ではその構造を整理し、「会社員時代の経験」「フリーランスを選んだ背景」「フリーランスがどのように立ち振る舞うべきか」について、私が考えてきたことを記載します。
既得権益構造とは

会社だけでなく、大小関わらず組織には既得権益を守る構造が作られていると思います。
- 既得権益構造が存在してしまう理由
- 年功序列や社内政治が、組織において重要事項とされていること
- それにより、成果よりも「上位層に気に入られること」が評価基準になってしまっていること
- その評価基準により、上層部が決まるので、悪循環を断ち切るタイミングがないこと
- 既得権益が守られる仕組み
- 出世した人を正しいことにし続ける文化
- 大きな責任を負わずに、権力と報酬を維持することが正しいとされる構造
- 短期間での成果を求めることで、長期的に正しいことを実行しようとしない風潮
私の会社員時代


私は会社員時代に「このままでは会社が衰退する」と危機感を抱き、組織や事業に変化を与えようと行動していた時期がありました。
結果からすると、既得権益を守りたい層から直接呼び出されて説得されたり、そもそもポジションから外されたりと抵抗にあい、ことごとく上手く行きませんでした。
(年代が近い30代とかの人とかにも抵抗されるので、こりゃダメだと思った記憶です…)
また、当時の若い私は「正しいことをすれば、必ず評価される」と信じていました。
しかし、現実は、成果を出すことよりも、既存のルールや立場を脅かさないことの方が評価される世界でした。
その経験を通じて「組織を変えることは難しい」と痛感しました。
なお、4社ほど日本を代表する大企業を渡り歩いてきましたが、どの会社も基本的には同じです。
「既得権益から奪う/活用する」を目指し、フリーランスへ


そこで私は方針を転換し、「変えようとして摩耗するのではなく、既得権益を外から利用する立場に回ればいいのではないか」と考えるようになりました。
実際に独立してフリーランスとして活動すると、既得権益にしがみ付く層の存在が、逆に自分にとっての収益源になりました。
具体的には、既得権益にしがみつく層は、自分で手を動かしたりすることはないので、新しい仕事が降ってきたときに、どうすれば良いかわからないので、とりあえず外注するケースが多く、そこで最初に名前が挙がるのがコンサルです。
ただ、コンサルは単価が非常に高い(マネージャー層だと400万円以上など)ので、長期で依頼する場合は、予算的に難しくなるケースも多く、そこで白羽の矢が立つのがフリーランスになります。
(一方で、とりあえず安い人手が欲しい炎上案件も多いので、そこは見極めが必要です。)
一方で、割り切って「既得権益から奪う」だけでは、自分自身の理想から外れてしまうことにも気づきました。
そこで、フリーランスという柔軟な立場を活用し、以下の指針で案件探しをしました。
✅対象の案件は、組織や事業に対して変化を志す活動かどうか
✅案件が見つかったら、とりあえず参加しながら本当に変化を望むかどうかを見極める
これにより、私と考えを同じくし、変化を志す組織に対しては、精一杯の力を使ってその変化の活動に参加し、実績を得るということを意識して、案件選びをしてきました。
この方針により、構造を逆手に取って稼ぎながら、自分の信念とも折り合いをつけられるようになりました。
【まとめ】フリーランスが取るべき理想の立ち位置


- 組織や会社を変えようとして摩耗するのではなく、構造を理解した上で戦略的に利用する。
- 募集案件や参加予定案件の組織が、本当に注力しようとしている内容や分野かどうかを見極める。
そうでないと分かった時点で、フリーランスという柔軟な立場を使って離脱を考える。 - 自信と同じ志を持つ組織には精一杯の力を使って、その活動に参加し、自身の信念を曲げない。
最後に


実体験として、既得権益構造や組織文化を、正しさで変えることは難しいと思います。
しかし、それを理解し、利用と選択的参加を両立することで、フリーランスは消耗せずに稼ぎ続けることができます。
大切なのは、まず「構造の存在を認知すること」。
その上で「自分がどう立ち位置を取るのか」を決めることが、自由で納得のいく働き方の第一歩になると思います。
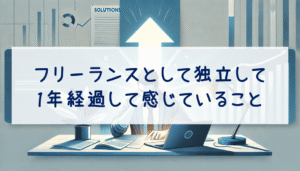
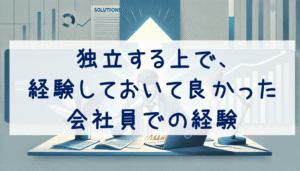
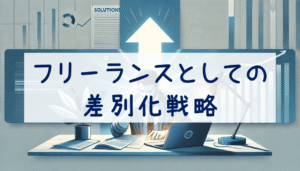
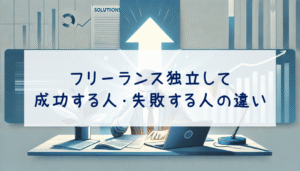
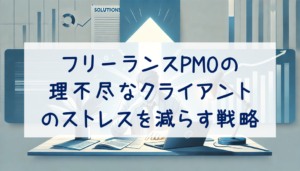

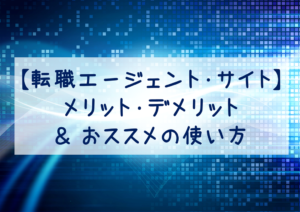
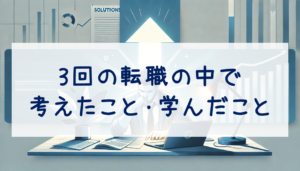
コメント